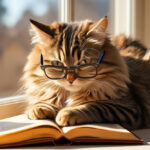こんにちは。【本を身近に】うらみわびの「本の帯」へお越しいただきありがとうございます。ここでは、当ブログが掲げる「理念」と「想い」をお伝えいたします。
- 素敵な本との出会いの場を創りたい
- 知的探求の一助になりたい
- 学校の外での学びに
- 本は人を助ける
- 言葉の力を信じる
素敵な本との出会いの場を創りたい
社会というものは、天気や風の具合で居心地がよくなったり、する木陰のようなものではない。それどころか、魔法使いが、雨を降らせたり、天気にしたりする奇跡の場所である。
アラン:著 白井健三郎:訳『幸福論』集英社
私の好きな哲学者アランの言葉です。
皆さんにもこれまでの人生のなかで、支えとなった言葉があるはず。それがこれまでにあった人の言葉であったり、本に書いてある言葉であったりします。
本には作者の想いが、熱が込められています。本は私たちに生きるエネルギーを与えてくれます。
近年、町の本屋が少なくなってきています。本との出会いの場が少なくなってきていることは悲しいです。ふらっと立ち寄った本屋で偶然手に取った本が思い出の一冊になる。そんな奇跡的な出会い。出会いのわくわくを届けたい。当ブログはそんな想いで立ち上げました。
知的探求の一助になりたい
本は私たちの知っている世界を広げてくれます。そしてわたくしたちの知らなかった世界を見せてくれます。でも、お仕事やお勉強でなかなか本に触れる機会がない、とういう人も多いはず。当ブログは、そんな人にも気軽に、良質な本との出会いの場を提供いたします。
「不偏」だから、あなたの「気になる」がきっと見つかる
当ブログには私の活きた言葉をつづっていくつもりです。その一方で、当ブログが私の感想や意見で埋め尽くされることは、ちょっともったいない気もしております。
当ブログは「不偏」を一つの指針として掲げております。それはどんなジャンル、どんな内容の本でも、「偏りなく」なく紹介していきたい。内容も、もちろん大切ですが、「こんな視点もあるのだな」という“気づき”にも焦点を当てて紹介していきたい、と考えております。
このブログには様々な性格、個性のある本たちが集まります。だからこそ、皆さんの「気になる」一冊がきっと見つかることでしょう。
また、当ブログでは、本を複数でもご紹介いたします。1冊でも十分でも楽しめますが、それが2冊、3冊あるともっと面白い!新たな視点や気づきが見つかるはずです。自己研鑽や学校の課題などに、ぜひお役立てください。
学校の外での学びに
学習指導要領の改定を機に、2022年度から高校における「現代文」が「論理国語」と「文学国語」という科目に変わりました。
ここではこの改定の良し悪しの論ははさみませんが、「文学国語」が選択科目となったことにより学校で文学文章に触れる機会が減っているのでは、心配しております。
本を読むことによって私たちは、思考力・忍耐力を養うことができます。したがって、私たちが学校や職場の外で本を読む機会を持つことの重要性がますます増してきていると感じます。
そもそも人に「読みなさい」と与えられた本よりも、自分が「読みたい」と思う本こそが、記憶に残り、ためになる本である、といえるでしょう。
古代中国の思想家である孔子は言います。
これを知るものはこれを好む者に如かず。これを好む者はこれを楽しむ者に如かず。
金谷治 訳『論語』岩波書店
つまり自ら好み、楽しんで物事を行う者こそが、本当に素晴らしい人である、ということですね。読書においても自分が楽しんで読める1冊が皆さんにとって価値のある1冊である、といえるでしょう。
当ブログは、皆さんが本と出合うきっかけをご提供いたします。
本は人を助ける
本に書かれている言葉は、ときに私たちを刺激し、成長させ、支えてくれます。
私自身、本に助けられました。前職で心を病み、働けない身体の状態がしばらく続きました。無味乾燥とした私に潤いを与えてくれたのが散歩と読書でした。
特に晴れた日の空の下で読む本は私の鬱屈とした気持ちを軽くさせてくれました。そんな自身の読書の経験を振り返ると、読書のもつパワーの大きさにあらためて気付かされます。
普段、本を読まない人に本を読む楽しさを知ってほしい。本を嗜む人に新たな良書と出合ったほしい。そこが当ブログの原点です。
言葉の力を信じる
言葉の力って本当にすごいです。
人が意志を持って他者を傷つけようとすれば言葉はナイフとなり、誰かを想う気持ちを持てば言葉は私たちを癒す包帯となります。
私はそんな言葉の力を信じています。ネットでは心無い言葉が日々飛び交う現在。だからこそ、人の心にじんわりと届く優しい言葉、人を奮い立たせる力強い言葉が、求められていると思います。
当ブログは、読者の皆さんに、そんな前向きな言葉を届けます。