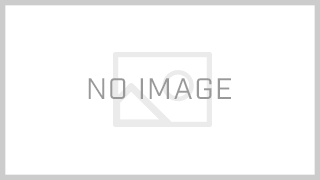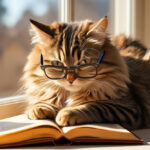「人間社会において最大の害があるのが怨望である」
福沢諭吉『学問のすすめ』斎藤孝:訳 筑摩書房
怨望(えんぼう)とは端的には、人を恨むこと。これが「最大の害である」と福澤氏は説く。
対して福澤氏は「不徳」という言葉で人間の至らない点をいくつか挙げている。例えば”怠ける“という行為。怠けてばかりいては仕事が進まなくて他の人が困る。これは良くない。しかし、”怠ける“という人間の性質の裏には、”安らぎ“や”安定“を求める、という気持ちがあるという。これは人間にもともと備わる性質でです。
また“お金にがめつい”という人は何かと人から疎まれがちだが、“お金を増やしたい”というのは人間の性であり、これによって経済というものが生まれ、私たちの生活が豊かになったといえます。
“怠ける”や“お金にがめつい”というのは、度が過ぎれば人から嫌われてしまいます。その意味では「不徳」といえるでしょうが、それらは人間にもともと備わった性質であり、また私たちの生活に必要な考え方でもあるのです。大切なのはそれらを用いるあんばいである、と福沢氏は言います。
しかし、そんな「不徳」の比にならないほど悪いやつなのが「怨望」であると福沢氏は『学問のすすめ』で記しています。怨望は際限がなく、自らになんのメリットもなく、ただ他者を害するだけである、というのです。
確かに相手に復讐しても、なにかスッキリしない後味の悪さは経験したことがあるな
福沢諭吉『学問のすすめ』斎藤孝:訳 筑摩書房
率直に相手と向き合う
怨みをかくしてその人と友達になるのは左丘明は恥とした。丘もやはり恥とする。
『論語』金谷治 :訳注 岩波書店
古代中国の思想家である孔子の文言をまとめたのが『論語』。孔子(B.C.552 0r 551-B.C.479)は先人の人たちが恨みがあるのに誰かと親しくするのを恥じていたのを引き合いに、自分も同じく恥と思う、と語ったとのこと。
ここからは人と接する時の“率直さ”が大切である、と孔子が考えていたことがうかがえます。自らの気持ち、殊に恨ましい気持ちを隠して人と接することは苦しいだけでなく、後々に災いを起こすことでしょう。嫌ならその人と付き合わない。付き合うなら本音を言おう。孔子はこのように伝えているように感じます。
『論語』金谷治 :訳注 岩波書店
三浦綾子さんの『残像』は北海道を舞台にした家族の気持ちのすれ違いと揺らぎをテーマにした小説です。真木家に突然現れた女性・紀美子。彼女は真木家の長男・栄介の子供を身ごもっている、と明かし結婚を迫る。しかしプレイボーイの栄介はそんなの知らない、ととぼける。後日、紀美子は自殺してしまう。紀美子の兄・治は妹の自殺の原因は栄介にある、として執拗に恨みを募らせる。
三浦綾子『残像』集英社
栄介の弟である不二夫は奔放な弟とは正反対のおとなしい性格。自分の気持ちをあまり表に出さない不二夫に怒るのが、東京から単身、北海道へ来た画家の摩理という人物。
「ぼくは……人が苦手なんです」
「黙りこくっていたら、人は傷つかないと思うのね。不二夫さんって。あなたは、だまってわたしを傷つけたわ」
「傷つけまいとすることも、あなたのようになっては傲慢よ。人間は弱いんですもの。傷つきやすいものよ。傷つけまいとして、人とろくに口をきかない存在なんて、目ざわりよ。至らぬために傷つけ合うことはあっても、それは仕方がないんじゃない?」
三浦綾子『残像』集英社
人に言わないことが優しさであることもあります。それが相手を傷つけないと思うから。でも言わないことで傷つくこともある。ここのさじ加減が難しいですね。
不二夫にも怒りの心がないわけではないと思うんです。きっと奔放な兄と同列に扱われたくないでしょう。執拗に真木家=悪 とする治に対して言いたいこともあるはず。むしろ人よりたくさんのことを考えているのかもしれません。プラス・マイナス様々な感情が渦巻くせいでとどまってしまう。進むべき道が分からなくて前に進めない。そんなもどかしさが彼の心の中にあるのかもしれません。
己に不足のあることを知れ
妹の無念を晴らそうとする治の心も重たいものです。栄介に復讐しても死んでしまった妹は帰ってこない。でも相手を責める気持ちをなくすわけにはどうしてもいかない……。果てしない葛藤が治の中にもあります。
大小、僕たちにはこういう経験がつきまとうよね
それでも怨望は人を救ってはくれない。怨望断ち切るには、己に不足のあることを知れ、と福沢氏は言います。物事の責任を相手に押し付けること。これこそが怨望の正体なのかもしれません。
最後まで読んでくださりありがとうございます。
本日も皆さんにとって実りある1日となりますように。
Number
- 福澤諭吉は4男5女の子だくさんだった。大家族の福澤氏は、人間の基礎としての家族の大切さと男女の平等を説いた。
- 三浦綾子さんの足跡を後世に残そうと、三浦綾子記念文学館が旭川駅近くに1998年に開館した。(三浦綾子記念文学館)
- 三浦綾子さんは将棋が好きだった。2001年から三浦綾子記念将棋大会が北海道で開かれている。
この記事で紹介した本たち
福澤諭吉『学問のすすめ』齋藤孝:著 筑摩書房
『論語』金谷治:訳注
三浦綾子『残像』 集英社
・本記事のサムネイル画像は”Canva”のAI画像生成により作成しました。
これはCTAサンプルです。
内容を編集するか削除してください。